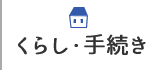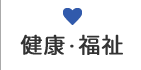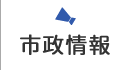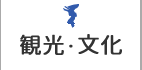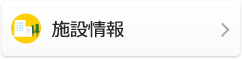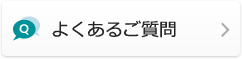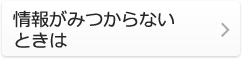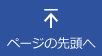2025年1月9日 令和7年徳島市消防出初式の開催について ほか
最終更新日:2025年1月28日
日時:令和7年1月9日(木曜日)午前10時30分から
場所:徳島市役所 8階 庁議室
年頭あいさつ
会見項目
1. 令和7年徳島市消防出初式の開催について
2. カスタマーハラスメント研修の開催について
記者会見資料
![]() 令和7年徳島市消防出初式の開催について(PDF形式:1,090KB)
令和7年徳島市消防出初式の開催について(PDF形式:1,090KB)
![]() カスタマーハラスメント研修の開催について(PDF形式:454KB)
カスタマーハラスメント研修の開催について(PDF形式:454KB)
会見の様子
注記:動画サイズ=約6.80 GB、再生時間=1時間8分49秒
年頭あいさつ
皆さま、明けましておめでとうございます。
まず冒頭に、先日開催された第71回徳島駅伝では、見事、徳島市チームが2年ぶりに優勝しました。
私も胴上げをしていただきました。大会前から胴上げすると言っていただいておりまして、有言実行で本当に嬉しかったです。
選手の皆さんには、年末年始で誘惑の多い中、体調をしっかりと整えてレースに臨んでいただきました。皆さんの努力に対して深く敬意を表するとともに、一生懸命に応援してくださった市民の皆さんにも感謝を申し上げます。
徳島市チームは、今まで何回も優勝していますが、一回も連覇がないようです。来年は連覇できるように頑張っていくと選手の皆さんがおっしゃっていました。ありがたいことです。
それでは、会見項目の説明に先立ちまして、年頭にあたり、私から少し述べさせていただきます。
昨年は、徳島市の中心市街地活性化が大きく動き出した一年でした。
今年は、新ホールの整備をはじめ、徳島市の未来を左右する重要プロジェクトが具現化に向けて動き始めると思いますので、常々申し上げておりますとおり、県と市がしっかり連携し、未来志向で新たなまちづくりに取り組んでまいります。
また、中心市街地の活性化を進める上で欠かせないのがアミコビルの再生ですが、先月26日に
さて、今年の4月13日からは、いよいよ「大阪・関西万博」が開幕します。
10月13日まで半年間の会期中には、世界中から多くの観光客が訪れると見込まれますので、インバウンドの拡大を目指す徳島市にとっても、経済再生に向けた大きなチャンスとなります。
昨年11月には香港と、また、12月には韓国との直行便が徳島阿波おどり空港から発着するようになりましたので、万博期間中に徳島の魅力に余すところなく触れていただき、終了後においても、引き続き徳島を訪れていただけるようしっかり
今年は、約800万人いる「団塊の世代」の全員が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者になるという超高齢化社会を迎えます。
いわゆる「2025年問題」と呼ばれているもので、社会保障費の増大や労働力不足など、これまで経験したことがないような社会の変化に、私たちは対応していかなければなりません。
現在、策定中の新たな総合計画においても、そうした人口見通しを踏まえた上で、いかにして持続可能な社会を築くかという視点を重視し、政策を進めていく方針を掲げています。
私も、今年、70歳を迎える年になりますが、今は本当に元気な高齢者の方がたくさんいらっしゃいますし、まだまだ社会のために貢献したいという思いを持たれ、実際に活躍されている方が徳島市には多くいらっしゃいます。
そういった皆さんに少しずつ力をお貸しいただきながら、国難とも呼べる人口減少・少子高齢社会に立ち向かい、誰もが幸せを実感できる社会にしていきたいと思います。
今年は「
また、
そのため、
今年は、まさに徳島市が変化し、発展するための大きな足掛かりをつくる非常に大切な一年になると思っています。
干支にふさわしい年とするべく、県をはじめとする関係各所との連携を深めながら、誰もが誇れる徳島市のまちづくりに取り組んでまいります。
市政記者の皆さまにおかれましては、徳島市の施策に関する情報提供や取材協力を行ってまいりますので、今後とも、市政情報の発信に格別のご理解とご協力をいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
会見項目説明
1. 令和7年徳島市消防出初式の開催について
今年も新春を彩る行事として、恒例の消防出初式を、アスティとくしまにおいて挙行いたします。
日時は、1月12日 日曜日、9時から12時まで。
消防出初式につきましては、新年を迎えるに当たり、消防職員・団員が職務遂行への決意を新たに、士気を高めるとともに、市民の皆様に消防に対する理解を深め、更なる防火・防災意識の高揚を図っていただくことを目的としており、昨年も多くの皆様にご来場いただきました。
内容につきましては、消防職員・団員、消防関係者等に対する表彰のほか、消防演技等といたしまして、地域においてご活躍いただいております、徳島市女性防火クラブ連合会の皆様や、徳島文理大学附属幼稚園幼年消防クラブの子どもたちによります演技の披露、また徳島市消防団 沖洲分団によります消防ポンプ車操法の訓練展示を予定しております。
また、ご来場いただいた皆様が、より楽しんでいただけるよう、さまざまなイベントをご用意しております。
屋内におきましては、火災予防について楽しく学ぶことができる「火災予防啓発コーナー」や「記念撮影コーナー」、また「消防体験コーナー」では『目指せ!消防士』と題して、防火服を着て消防ホースを延ばしたり、救助ロープの結び方や心肺蘇生法を学んだり、実際の消防士の仕事を体験することができます。また、体験していただいた子どもたちには、かわいい消防消しゴムや、今回、徳島製粉様からご提供いただきました、徳島市消防局限定パッケージの金ちゃんヌードルが当たるガチャガチャもご用意しております。
また、屋外におきましては、ミニ消防車の乗車体験や起震車による地震体験、徳島市が誇るはしご車や最新鋭の消防車両を展示するほか、救助隊がアスティとくしまの屋上からロープで地上まで降下する訓練展示を行い、フィナーレには、消防ポンプ車による一斉の祝賀放水と、徳島県消防防災ヘリコプターによる祝賀飛行で締めくくります。
詳しい内容につきましては、徳島市ホームページのほか、徳島市消防局公式インスタグラムでもご覧いただけますので、一人でも多くの皆様にお越しいただければと思います。
2. カスタマーハラスメント研修の開催について
徳島市では、市民サービスの更なる向上・改善に向けた職員研修の一環として、近年、様々な業態で課題となっております「カスタマーハラスメント」をテーマとした研修を、昨年10月に包括連携協定を締結いたしました株式会社テレコメディア様のご協力のもと、本市では初めて開催いたします。
開催日時等につきましては、今月20日(月曜日)の午後2時から、徳島市役所13階におきまして、主に市役所や出先機関において窓口業務に従事する本市職員30人程度が参加いたします。
研修内容につきましては、カスタマーハラスメントとクレームの違いや、クレームを減らすビジネスマナーなど、カスタマーハラスメントに関する知識や理解を深めるものとなっております。
研修講師には、株式会社テレコメディア様のお客さま本部において、長年、社員教育に携わっておられます 教育訓練部長の
本研修を通じて、本市職員が「カスタマーハラスメント」に対する正しい知識や理解を深めるとともに、日々の業務におけるビジネスマナーやコミュニケーションスキルをより一層向上させ、質の高い市民サービスの提供に引き続き努めて参りたいと考えております。
質疑応答
1 会見項目
(幹事社・朝日新聞社)
幹事社から今の質問項目に対しての質問をさせていただきます。
出初式なんですけども、参加規模は大体どれぐらい想定されているのかと、今年ならではの取り組みをお聞かせいただけますか。
(市長)
来場者の方は去年が1500人だったということですね。今年もそれぐらいかなということであります。
消防職、それから消防団員、関係機関合わせておよそ470人。消防車両が21台ということになっています。消防局がおよそ150人で12台、消防団がおよそ210人で9台ということですね。それから関係機関は、徳島市女性防火クラブ連合会がおよそ80人、徳島文理大学附属幼稚園幼年消防クラブがおよそ30人ということになっています。
例年と違うことというのは、何かありますか。
(市担当者)
消防局から説明させていただきます。開催内容につきましては、昨年と同じ内容とさせていただいております。
昨年度に内容を見直したところでございまして、来場者の皆様により魅力的で、楽しんでいただけるイベントになるような内容としておりますので、よろしくお願いいたします。
(幹事社・朝日新聞社)
あともう一点、カスタマーハラスメントですが、直近の統計とかで、市役所でこのカスハラがどれぐらいあったかっていう事例のデータはありますでしょうか。
(市長)
とりあえず表に出ているといいましょうか、徳島市は「徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例」というのを制定しておりまして、市民等から要望を受けた場合には、要望等の記録票を作成しておりまして、令和5年度に作成された要望記録票のうち、不当な要望、または不当要求に該当すると思われる件数については、7件だったということでありますが、実際はもっとあるのではないかと認識しておりますが、出ている数字は7件ということです。
(幹事社・朝日新聞社)
その7件は具体的にどういった内容なのか、差支えのない範囲で教えていただけますか。
(市担当者)
人事課の方からご説明をさせていただきます。
そちらの7件につきましては、市のホームページの方でも概要の方を掲載させていただいておりますので、また見ていただけたらと思いますが、大きな部分としましては、例えば市役所等の窓口において、何らかの手続きを職員が説明した際に、ちょっとご納得等をいただけず、例えば相手の方が威圧的な言動を職員に対して繰り返すような事案が複数報告されております。
(幹事社・朝日新聞社)
あと一点だけなんですけど、市では初めての研修ということですけど、県内では初めてなのか、その辺はどうでしょうか。
(市担当者)
繰り返し人事課の方から説明させていただきます。テレコメディア様の方でお聞きさせていただいている部分では、これまで3回、徳島県警察本部ですとか、徳島大学病院また四国大学の3カ所で、同じようなカスタマーハラスメントに関する研修をされておるとお聞きしております。
(市長)
テレコメディアさんが関係してる分ということですね。ということで独自にしてる分についてはちょっと調べておりません。
(幹事社・日経新聞社)
日経です。
細かい話で事務方に伺った方がいいのかもしれないですが、今のカスタマーハラスメントに関する話で一つ伺います。
今回研修を初めてやるということですけども、それ以外にカスタマーハラスメントに対応する取り組みで、市として取り組んできたこと、取り組んでいること、何か主なものがあれば教えていただきたいという質問です。カスハラに限った話ではなかったと思うんですけど、前の市長時代に確か(職員の)名札を名字だけにするとか、プライバシーの保護に絡んでという施策もあったかと思うんですけども、その効果みたいな何か、数字では出ないんでしょうが、それによって現場で変わったというような状況があるかどうか、その2点伺います。
(市担当者)
まず一つ、カスタマーハラスメントの取り組みということで、今、日経の記者様の方からご説明いただいた部分で、昨年、令和6年3月から課長補佐以下の職員に係る名札につきまして、名字だけ、そして、名字についてはひらがな表記という形に改めさせていただいたというのが、取り組みとしてはあります。
というところで大きな取り組みとしてはまずそちらが大きなところだと思います。その効果につきましては、具体的に直接数字で見える部分がちょっとございませんが、当然窓口で働く職員にとっては、近年カスハラが注目されておりますので、そういう部分では安心感というのも出てきておるんではないかと推測しております。以上でございます。
2 その他項目
(幹事社・朝日新聞社)
朝日新聞です。
先ほどご挨拶にもあった通り、中心市街地の活性化であるとか、新ホールの重要プロジェクトの具現化に向けて動き出すとおっしゃいましたけども、改めて今年度ですね重点的に取り組みたい施策とその意気込みを聞かせていただけますでしょうか。
(市長)
動き出さなければいけないことというのはいっぱいありましたね。もう早くしないといけないことはたくさんあるんですけれども、ゴミ処理施設ですね。徳島市としては、早く進めていきたいと思っております。3月には方針が決定できると思いますので、また皆さんにも発表させていただきます。
それから県が計画していますアリーナがあります。これも、急がないとという気持ちはあります。県市協調でぜひ取り組んでいきたい。高松に立派なのができまして、だいぶ差がついてるなみたいな感覚があるんですけれども、アリーナもしっかりと取り組んでいかなければいけないと思っています。
その他、年頭の、中央卸売市場で申し上げたんですけれども、中央卸売市場、(建設から)50年超えているんですね。かなり老朽化が進んでおりまして、働く方の安全のため、それから出荷している方とか消費者の方の信頼を得るためにも、やはり施設の更新をしていかなければいけないというのを強く思っているところです。更新するにあたって、これまでの中央卸売市場の機能だけでなく、道の駅機能と言えばわかりやすいんですかね、誰もが食べられたり、誰もがお土産買ったりとかですね、そういう施設も併設するということを考えております。
それから防災の拠点にもなりますね。いざというときの食料基地にも最適ですよね。いざというときの食料基地にもなるようにしっかりと取り組んでいきたいと思ってます。
市場の関係者の方とお正月にいろいろお話したんですけれども、とにかく早く目途を立ててほしいといろいろ要望がありました。ご意見もかなり承りました。テーマパークにしたらとか、市場の方がいろいろ案を持っておりましたんで、たくさんの方のご意見を聞きながらしっかりと良い施設の整備、そのスタートを切りたいなと思っております。
あといろいろ申し上げたんですけど、中央卸売市場はもうとにかく早くする、早くしないといかんことがいっぱいあるんですが、私ずっと懸案事項として引っかかっておりましたのが、旧動物園跡地ですね。動物園の跡地がずっとそのままになっております。もう何十年も経っておりますので、早く何か目的を持ってやらなければいけないと思っているところです。
それから木工会館もずっとそのままの状態になっておりますね。木工会館についても、ちょっと動き出したいなと思っております。
その他いろいろありますが、今思いつくことを述べさせていただきました。
(幹事社・朝日新聞社)
新ホールなんですけども、県市協定の改定について、議会の議決を必要とするという条例案の再議がまだ継続審査のままですけども、今後の見通しであるとかどのように取り組まれていくお考えなのかお聞かせいただけますか。
(市長)
議会がですね、議会のルールに基づいて今やっていただいているということですから、私達はしっかりと説明をするということですね。議員の皆さんと相談して、できるだけ早く結論を出していただけるようにお願いをしたいと思っております。
(幹事社・日経新聞社)
新ホールの再議の件で、これは市長としてデッドライン、2月議会はこの後予算関連でありますけれども、市長としてデッドライン、ここまでには再議をという設定は、お考えはありますでしょうか。
(市長)
ありません。
ここまでにしなければいけないということは特にありません。
(幹事社・日経新聞社)
ただなかなかそこができないと話自体が先に進めない側面もあるだろうと思いますけれども、あくまで、なるべくできるだけ可能な限り早くという。
(市長)
可能な限り早い方がいいということはもう間違いないんですけども、ここまでにとか、そういう日にちの設定は何もしておりません。
当然早くしていただけるに越したことはないとは思っております。
(NHK)
NHKです。
中心市街地(活性化)の話で、目処がついた案件だと僕は思ってるんすけど、新町西の再開発、B工区も工事業者が決まって、これで完成まである程度目途がついたかなと思ってるんですけども、新町西といったら市長が前のときにホールの白紙を公約に掲げて当選されて、今の形が見えてきたと思うんですけども、今回工事業者が決まってある程度目途がついたことに対してのちょっと受け止めをお伺いしたいんですけども。
(市長)
もう工事が始まっておりますので、できるだけ早く完成させていただきたいという気持ちではあります。
(NHK)
完成したらどういう効果、どういう期待を持ってらっしゃいますか。
(市長)
よく言われるのが、徳島駅前から阿波おどり会館、眉山に向かって歩いたときに西新町、古い建物が建っておりましたんで、日経新聞さんでしたっけ、日経新聞さんの全国のコラムに書かれたことを思い出してるんですけど、眉山に歩いてると、あの西新町の景色が非常に悪いということを書かれてたのを、もうかなり前です、もう七、八年前のことかと思いますが、それがかなり印象に残っておりますけども、それは解消されるのではないかというふうに思っております。
(NHK)
マンションが多いと思うんですが、経済的な効果はどうですか。
(市長)
経済的な効果は、ホテルも入っておりますので、当然あると思います。
マンションもそうですね。大勢の住民が増えるということですね。マンションが何戸でしたっけ、結構できると思いますけど、そこにそれぞれのご家族が、個人の方もいらっしゃるかもしれませんが、住んでいただけるわけですから、もう人が増えるということは町が活性化するということですから、その点は大変ありがたく思っています。
(NHK)
大変失礼な聞き方で申し訳ないんすけども、市長が今回ホールをあそこ(徳島市文化センター跡地)で作るのは白紙にされて、今回の形になったと思うんすけども、今現状ホールのことも含めて考えられて、あのときの判断ってのは間違ってなかったなっていう思いでいらっしゃいますか。
(市長)
当時ですね、市民の皆さんの70%以上の方が反対ということを表明されておりました。
それを受けての私の行動であったわけでありまして、間違ったという印象はありません。ただ当時の事業というのはかなり不透明なところがありましたので、いきなり56億円も事業費が上がったとかですね、全く説明がつかないことが多々ありましたので、そういうことに対する市民の不満といいましょうかね、そういうのがあったと思います。それを受けての行動でありましたので、特に反省するところは何もありません。
(NHK)
ちょっと全然別の話になるんですけど、市長も最初おっしゃったインフルが昨日県から発表があって、徳島市を含む徳島保健所が2倍までいかないですけど、2倍近くになってると思うんですけども、現状それを今後市として対策とか立てられていくご予定はありますか。
(市長)
対策といってもなかなか難しいんですけど、皆さんに予防行動を呼びかけるということですね。もう基本は手洗いとかうがいとかですね。人混みではマスクをしていただくとかですね、皆さんに、今大変なんですよ、ということをしっかりと認識していただくということかと思っています。徳島市の夜間休日急病診療所、ふれあい健康館も大変な事態になっていたようですね。元日、日勤の先生とちょっと話したんですけど、日勤の先生が帰るまでに270人の方を診察したと。それもほとんどインフルエンザで。帰るときに、まだ100人以上の方が残っていたと。受付が10時半までということなんですけど、先生が診察が終わるのは午前3時とかですね、そういう状況なんだそうですね。もう本当に大変なことになっていますので、誰もかかりたくはないと思うんですけど、私も当然なんですけど、どこで感染したかっていうのはわかりません。全く心当たりがありません。感染というのはそういうものなんですね。咳してた人が近くにいたとかそんな印象も全くないんですけれども、知らない間に感染していたということで、(インフルエンザが)流行っているときには人混みには行かない方がいいんですよとかですね、しっかりうがい手洗いしてくださいとか、1人1人が意識を持っていただくということ以外にないのかなとは思います。
(NHK)
元日は視察か何かで行かれたときに先生とは話をされたんですか。元日にふれあい健康館の先生と話をされたって今おっしゃったと思うんですけども、それはどうしてふれあい健康館に行かれたのか。
(市長)
医者の中に知り合い、友人がいまして、友人の方が知らせてくれました。こういう状況ですということで。その方は、当番医として徳島市の夜間休日急病診療所で診察をしていただいた方で、その方が診察が終わったときに今こんな状況ですということを知らせてくれました。
他にも民間でも元日開いてるところっていうのは協立(病院)ができてましたね。成人式に行くときに道を走っていまして、八万町でかなりの行列ができてるんですね。
何かを買う行列かなって一瞬思ったんですけど、見ましたら、病院だったんですね。
当然開いてる時間なんですけど、病院に入れなくて、かなりの行列ができているのを見ました。そういう状況です。お気を付けいただきたいと思います。
(NHK)
ちょうどインフルで危険度が高いというと、やっぱり学校とか高齢者施設だと思うんですけども、今対応が難しいとおっしゃったんですが、その辺の対応、市としてどういうことをしていきたいとか特にはないですか。
(市長)
今のところ徳島市としての対応ということはありませんが、市民の皆さんに気をつけてくださいとしっかり広報していかなければいけないというところはあります。確かにね、集団の中で感染するっていうのはマスクをしていただくということぐらいしかないんですよね。手洗いうがいとマスクとあと何がありますかね。そういうのをしっかりと呼びかけていくということだと思います。当然学校では先生方が注意して、子どもたちにはしっかりと呼びかけていただいてると思います。
(NHK)
患者さんがこれ以上増えたり、現状維持でずっと高止まりしてる状況が続くと、医療体制なり市の全体を見て、どういう危機感があるっていうふうに考えてらっしゃいますか。
(市長)
今も史上最高とかいう言葉も聞かれるぐらいの数ですよね。もうこれ以上増えたら、医療機関にかかれないという方がたくさんいらっしゃって大変な問題だと思います。
特に高齢者の方は命の危険がある可能性があります。今、医薬品が不足してるんですよね。私も年末にインフルエンザで、インフルエンザの苦しい期間ってのは2日ほどだったんですけど、咳が出るんですけど、咳どめの薬がこんだけしか出せませんというような感じだったんです。あんまり入ってこないんです。ということで昨日ニュースを見てましても、これインフルエンザの薬そのものがもう不足しているっていう話なので、これはもう大変なことです。特にインフルエンザって命に関わる問題ですから。特に高齢者施設で、もし感染が広がったとしても大変なことになると思いますので、危機感を持ってしっかりと皆さんには呼びかけていきたいと思います。
これはマスコミの皆さんにもぜひお願いしたいと思います。私達が呼びかけるよりも、マスコミの皆さんが市民・県民に対して、国民の皆さんに対してしっかり繰り返し伝えていただくと、皆さんの意識が変わってくると思いますので、皆さんに対する注意の呼びかけというのはぜひマスコミの皆さんもお願いしたいと思います。
(NHK)
今ある程度やっぱり危機感は持ってらっしゃるんですね。わかりました。
(市長)
薬がないっていうのも大変な問題だと思います。万が一インフルエンザになっても特効薬がありますから。私もびっくりしました。1回飲んだらいいと言ってるんですね。
できるだけ早く飲んでくださいと。いつでもいいんでって。1回飲んだらそれでウイルスが抑えられるということですから。その薬があるとないとでは大違いです。当然若くて体力のある人だったら、それは1日ぐらい余計にかかるだけで回復するかもしれませんけど、高齢者で体力のない方だったら当然命に関わってくることですから。大変な問題だと思います。
(NHK)
先ほどホールの話もありましたけど、去年から含めて議会対応ということで、傍から見てもなかなか議会との関係がちょっとギクシャクしたところもあるかなっていうふうにちょっと思ってたんですけども、今年は議会に対してどういう対応をしていこうとかっていう意気込みというか、考えとかってお持ちですか。
(市長)
これはもう今年はということでなく、私は就任当初から、議会軽視と言われないようにしっかり説明することは説明する、報告することは報告する、それでしっかりとやっていきたいっていうのはずっと思っていたところであります。その意識は当然今も
思っております。
(NHK)
ちょっと失礼な聞き方ですけども、それをされてたと思うんですけど、去年も半年余りはやっぱりちょっとギクシャクしたところもあったと思うんですけども、それで今年になって改めて市長としてこういう一歩を踏み出すというか、こういう新たな考えがあるっていうところはどうでしょうか。
(市長)
私は議会に対しては自分でできる最高のことはしなければいけないということを思っていましたので、それ以上何をしたらいいのかと聞かれてもなかなか難しいとは思います。議会の皆さんに議会軽視と言われないようにしていくにはどうすればいいのかということで、当然職員とも話はしておりますし、今後ともそういう対応をしていきたいと思います。ただ今回、議会軽視というふうに言われてますけど、それはちょっと違うんではないかと思うところはあります。つまり、二元代表制であるから、市長が知事と話し合って決めてきたのは議会軽視だと言われてるんですけど、二元代表制であるからこそ、それぞれに責任があるわけです。当然議会としては、議決機関でもありますし、私達のことをしっかりチェックするっていうのは議会の仕事だと思います。私が知事と話し合って、同意した、合意したというのは、これは私の責任なんですよね。それを議会に諮らなかったということで、議会軽視と言われてるんですが、その件に関してはですよ、他のことは言ってません、その件に関しては、私は議会軽視ではないと思っております。
つまり、二元代表制だから一方の代表である市議会に大事なことを諮らずに決められないというのではなくて、それぞれに役割があるんですよね。議会の権限ってのは非常に大きいです。私達が何かをやりたいって言っても予算を認めていただけなければ何もできないわけです。
ただ、議決をしていただかないと、例えば今回の件との話とかを考えてみましても、議会に諮るというのは、例えば30人の皆さんに全部回るのかとかですね、議長だけでいいのかとか、権力を持っている方に聞くのかとかですね、これって難しい問題ですよね。30人の方の意思を統一していくということは私にはできないことです。ただ今回の件は、議会に対してしっかりと報告をする、ということで、県ともお話はしておりました。知事と会って話をしたときに、文書にもなっておりますけども、お互いに、県議会・市議会に対してしっかり説明をしていこうと。文書にもなっております。私はこの件に関しては、議会に報告をしっかりするということでいいことだと思っておりました。それが二元代表制でないかと思うんです。私の責任で自分の責任を全うしたと言いましょうか。つまり、議会で30人に聞いて多数決するんだったら、それこそ市長はいりませんね。全部議会で決めるということになりますし、声が大きい人の意見だけ聞くのかというのもちょっと難しい問題なんです。
実は私、前に市長だったときに、専決の決断をしたときに、発表する前に議会に申し上げたことがありました。そのときにですね、わかりましたというね、それはそれしかないなみたいなこと言われたんですけど、実際かなり議会から責められました。当然、議会としては、議会の議決を経ずして予算を使ったわけですから、当然だと思います。ただ事前に事情の説明をしていたんですけれども、それは何の役にも立たなかったというかね。議長さんは納得してくれたんですけれども、それは何にも結局議会として、そんなことしたらあかんよというお叱りを受けたということはありました。
今回のこともちょっと考えていただきたい。これすごく難しいですよ。
例えば、県と合意するにあたって、同意するにあたって、議会の皆さんのご意見を聞いたとします。当然反対の声が多かった場合に、その声を聞いてですね、私は反対せないかんのかとか、そういう問題があるんです。つまり、議会に諮るということは、議会の大多数、半数以上が県と合意したらあかんってもし言われたときに、私もどうするべきなのかということですから。これ議会の議決が必要でなく、方針の決定ということは、執行機関である市長ができるわけですよね。ですから、意見聞いて、それと違うことを県にはできないっていうことが当然あります。意見聞いて、反対、反対、反対と言われたりなんかで、賛成っていうのは言えない、そういう難しい問題もあるんだろうなと私は考えたところです。これ難しいですよね。議会に諮って、あかんって言われて。いや私としては絶対に受けるべきだという。記者の皆さんにも言いたいんですけど、もし同意してなかったら、合意してなかったら、どんなことになったと思いますか。議会が市長の動きをチェックするっていうのはもう当然その権限があります。ただ、それは市のために、市民のためにならんことをした場合にですね、当然私は議会から言われるわけですけども、今回の件に関しては、市のため、市民のためにこれ以上のことはないという判断で決断をしたわけです。市のため、市民のためにこれ以外の判断はないと確信を持って決断をしました。私何回も言ったんですけど、皆さんが市長をしていても絶対に受けました。これ市議会議員の皆さん30人の方、どなたが市長であっても間違いなく受けたと思います。これは合意しないといけない問題です。
つまり市の利益っていうのはもちろん財政だけの問題ではありませんが、私も議会でも申し上げましたけど、早く作ってくれっていう市民が非常に多いわけです。とにかく一刻も早く作ってほしいと。こっちが賛成、こっちが賛成という方は当然いらっしゃいますけども、どっちでもいいから早くしてくれという方が非常に多くいらっしゃったということですよね。その中で、県が県の予算で県の土地に建てるっていう判断をしているわけですから、それを否定するということは、市が建てないといかんことになる可能性があるわけです。
委員会で妄想じゃないかとか言われましたけど、妄想でなくて可能性なんですよね。可能性はあるんですよ。だって、協定が破棄された場合、これ元々市の事業ですから。県議会の方も言うてましたよね。県議会議員の方で、市が反対しているのに、市議会があれだけ反対しているのに、何で県が建てないといけないんだというご意見を持ってる方も当然いらっしゃいます。ですから、とにかく早くしてほしいというときで、あの9月の知事との話で、私が判断をしなかった場合、市議会に聞いてきますと言った場合ですね、9月議会には予算は上げられませんでした。ですから、間違いなく遅れたわけです。それで11月の県議会に改めてあげていただけるかどうかっていう保証は全くないんです。つまり協定が破棄されたら、「これは市の事業だから」ということは当然あります。今回ご提案いただいたのは、徳島市にとって徳島市民にとって、これ以上ない、私が想定していたよりも遥かに良い条件を出していただいたんです。それで、合意しない、同意しないっていう判断があるのか。報道の皆さんにも本当にお願いしたいんですけども、市議会で言われてることを、つまりさっき申し上げました二元代表制だから、議会軽視の最たるもんだというふうに言われているんですけど、いやいや二元代表制だからこそ、これは市長の責任で決めるもんでしょっていう、そういう意見も載せてほしいです。
つまり、その意見だけが出ると私がかなり悪いことをしてるようなイメージになりますよね。実はね、年末年始、年末はあんまり最後の2日ぐらいだったんですけど、いろんな人と話をして、私に対してね、結構怒ってる人が多くいました。議会軽視って思っているわけですね。それで、いろいろ言われました。それで、説明したらみんな納得してくれるんですね。これ当たり前やなと。謝ってくれた人もいました。話聞いてよかったっていう、そんな話をして、私は市民の皆さんにも、議会の皆さんにも、マスコミの皆さんにも、こんな当たり前だろうと思うことでもちゃんと説明していかないかんのだろうなというのを感じたんです。それでしっかり説明していこうというのがさっきの方針です。しっかり説明していかなかったら、マスコミの皆さんもわかってくれているだろうなと思っていても、驚くような記事が出るわけですよ。個人といったり、執行部といったり、二転三転しているって書かれてますけど、二転三転って書かれるのは非常に私は残念に思います。
徳島市長が個人で決断したということは、私確信をもって言ったんです。つまり、個人というのは、市議会の委員会で、市議会の意思が入ってないということに対して、その場を収めるためにですね、徳島市長が個人で言ったと。その報告を受けたときに、徳島市長がというのはちゃんと言いましたというふうに私受けました。徳島市長が個人で判断するっていうのは、皆さんも地方自治法見ていただきたいんですけど、徳島市長というのは執行機関なんです。徳島市長、執行機関が判断するわけですから、個人で執行機関ですから。ですから、私は言い訳のために個人だ、執行機関だって言ったわけではないんです。それをわかっていただきたいんです。つまり、徳島市長が個人で判断したっていうのは、執行機関の判断とイコールですよっていう説明をしたんです。それが二転三転というのは。二転三転というのは実は私に対する問責決議で書かれとった言葉です。それを見て、引用したんだったらぜひ反省していただきたいなと思うんですけれども。
説明したんですよ。二転三転したわけではないという。こういうのももうわかっていただけるんだろうなというのではなく、しっかりと説明をしていきたいなと思っております。
(NHK)
現状こういう説明とかをしっかりされてきたと思うんですけども、今、日経さんの質問にもありましたけど、再議がなかなか今結果が出てない状況、このまま見通しが全くない状況をどう改善していくかっていう部分で、今後どういう議会対応をされていきますか。
(市長)
当然聞かれたことに真摯にお答えするということですね。あと議会には早く議決をしていただきたいというお願いはしたいと思いますけども。議会が議会のルールに基づいてやっていることに対して、私達がその点に対して言うのはちょっとおかしいかなと。言うべきでないかなと思っております。
(NHK)
でもやっぱりこれまでしっかり説明もしてきたっていうご認識でいらっしゃるんで、それを今年もそのまま続けていくっていう。
(市長)
例えば9月のことについて議会に対しておかしいと言っているでしょう。二元代表制が根本的に間違ってませんかと。二元代表制だからこそ、市長の責任のことがあるんですよ、ということを言っているわけですから、つまり、言っている以上ですね、私他のことに対して議会に対してはより気をつけてしっかりと説明責任を果たすし、報告もしっかりとしていきたいというのを、この点おかしいと言っている以上、自分がおかしいと言われたくないので、しっかりと責任を果たしていきたいというふうには思っています。
(徳島新聞社)
徳島新聞です。
先ほどのNHKさんの質問に関連してなんですけども、市長の中で合意と同意と何回か繰り返されるんですけど、合意と同意は何か違いがあるんですか。
(市長)
実はですね、私はどっちでもいいと思っているんです。どっちでもいいと思っているんですけど、一旦使った言葉と違う方を言ったら、また言われたら嫌かなと思うんで、どっちだったかなと思いながら今喋ったぐらいで。
(徳島新聞社)
どっちでも違いはないということでよろしいですかね。
(市長)
日本語的に言えば、提案されたことに対して同意したというのが正しいのかもしれません。それで、知事との会談の後にすぐに申し上げたのが、完全合意ではありませんということを記者さんの前では言いました。そのときは合意という言葉を使っておりましたけれども感覚的に大きな違いはありません。
(徳島新聞社)
これまでの市の方の説明で、市長が個人で同意したと、それは市というか組織でのご決定ではないというようなあれがあったと思うんですけど。ということは、議会に説明したらもう完全に組織の判断と。今はその過程なんですかね。議会との同意を得られて市として合意できるという段取りと。
とにかく市長個人で判断されたけど、市の判断ではないとか、なんか紛らわしいんですよね。
(市長)
おっしゃる通りで、大変申し訳ありません。
確かにね、個人という言葉は本当に使ってはいけない言葉だったと思います。もう間違いなく皆さんに誤解を与えました。前に、朝日新聞の記者さんに言われたんですが、それは紛らわしいですよって言われまして、確かに紛らわしいなと。その点は確かに反省しています。ただ、私としては、市長個人が執行機関であるという意識で行動はしてます。
副市長は執行機関でないんです。副市長は執行機関の補助なんです。つまり執行機関は私なんです。だから市長は個人で執行機関なんですよっていう。紛らわしいですね。確かに紛らわしいですけど、報道関係の皆様にはそこら辺をわかっていただきたい。地方自治法に副市長は執行機関の補助って書いてありますから。だから、執行機関というのは市長だけっていう、そういう感覚、それが正解なんですよね。そこを私は意識しとったわけです。ですから、二転三転では決してないというのは申し上げたい。ただ、もう本当に謝りたいです。確かに紛らわしい。個人って紛らわしいですね。ただ記者の皆さんにはぜひわかっていただきたいということです。
私は最初から「個人」で逃げるという気持ちは全くないですから。私は自分の責任でしっかりと判断して、これが市のため、市民のために、これ以外のことはないというかなり自信を持って判断したことです。それを「個人」という言葉を使って逃げているのかと、そんなことは全くありませんから。市長は個人で執行機関であるということを念頭に申し上げていたということです。使うべきでなかったんですけど、議会が入ってないって言われて、個人と言わないと納得してくれないということから始まってるわけです。そこで個人という言葉が出て、私が議会の皆さんに説明するときに、それと違う言葉を使ってくれるなと。また議会が混乱するよということになりまして、不本意ながらではありますが、紛らわしいだろうなと思いながらではありますが、自分自身の中では、個人が執行機関であると確信して言っていることですから、ここで違う言葉を使って、またそこで混乱したらいかんなという意味で、間違いでないので使ったということです。
ただ記者の皆さんだったらこうやって説明できるんですけど、一般の市民の皆さんがあの報道を見て、市長は自分で言うたことを、「あれは個人だから」と、責任逃れしとるように思った方がいっぱいありました。直接話したら、「ああ、そうだったんですね」と皆言ってくれるんですけど、確かに説明するのは難しい。紛らわしいことはいっぱいあるけど、皆さんもわからなかったら聞きに来てくださいね。もう何でも答えますので。とにかくしっかり説明してですね、今回のような誤解の報道がないようにしっかりしていきたいなと思っております。
(徳島新聞社)
11月の臨時議会で再議についての継続審査があったときに比べ、この間あった12月議会の場合は、継続審査に賛成する議員が増えていたと思うんですけれども、総務委員会に限ってもそうだと思うんですけども、継続審査に賛成する議員がちょっと増えてきたということに関しては市長の受け止めはどうですか。
(市長)
なかなかそれ答えにくいですよね。継続審査に(賛成する)増えた人を批判するみたいなことになってもいけませんし、なかなか答えにくいですけど、議員の方がそれぞれ判断されてきたことです。その人を批判するような発言をしてしまったら困るというところですけど、個人それぞれの議員、30人いらっしゃいますから、皆さんが選挙で選ばれた人なんです。その1人1人が自分で決断して決めたことですから、私がその人に対して言うのはちょっとおかしいかなと思います。
(徳島新聞社)
ちょっと質問戻ってしまうんですけど、動物園跡地について市長の方で何か考えられてることってあるんですか。
(市長)
これはなかなか決まるまで言えないですよね。
市の職員に対してしっかり提案してほしいということも申し上げましたし、いろんなところで皆さん良い意見ないですかって、いろんな方に呼びかけたりはしております。良い案が出ればいいんですけども、今皆さんに申し上げるようなことはありません。
(四国放送)
四国放送です。
徳島都市開発の件で先ほど冒頭でも触れていただきましたけれども、改めて民間出身の初の社長の南波氏の印象と、期待について教えていただけたらと思います。
(市長)
南波氏の履歴といいましょうか。これまでの仕事というのは見ていただいたと思いますけど、私も最初に彼の経歴を見て、おっと思いました。もうデパートの中で部長を務めてかなり活躍していたと。デパート関係者からも彼のことについては伺いました。かなり活躍していた。コンサル的な仕事もして、今はもう徳島に、一昨日ですよね、引っ越しが終わって来ておりますけど。岩手県でデパートの再生に取り組まれたんですよね。その話も私も伺いまして、これはなかなかいい人が見つかったないうことで、本当に喜んでます。もう彼の経験、人脈全てに期待をしております。奥さんと一緒に来られたんですね。だから腰掛けではないと。徳島市民になって、徳島市のために頑張りたいというふうにおっしゃっていただいてる彼を徳島市としてもしっかりと支えてやっていきたいと思っております。
(四国放送)
これまでの議会の中で、改めて市の融資した20億円の使い道について、外部の委員会を立ち上げて検証するという話もありましたけど、今のところ進捗状況はどうなっていますか。
(市長)
はい、やっています。やっていますが、ちゃんと発表できるようになったら発表したいというところです。
(四国放送)
今検討を進めているっていうことですね。
(市長)
スタートはしております。進んでおります。
私嘘はいませんので、どこまで言うたらええかなというところで、ちょっと今迷いがありましたけれども。
(市担当者)
まだ具体的に、結果は出てないんですけども、進めるということで今着手はしております。
(市長)
着手をしているというところで、まだ皆さんに具体的に説明することはないというところです。議会でも約束しましたんで、もう絶対やりますから。
議会というか選挙のときにね、もう約束してました。必ず情報公開をしっかりしていきたいということを申し上げておりましたんで。公約でもありますし、議会でも約束したことでありますので、必ずやります。もう着手はいたしました。
(四国放送)
いつ頃までにとかいう目途はあるんですかね。
(市長)
今のところ発表できることはないです。
(時事通信社)
時事通信社です。
発表事項と被ってしまうのですが、来年度の当初予算についての考えをお聞きしたくて、先ほどお話の中で2025年問題について言及がありました。徳島県は特に少子高齢化が深刻な県で、課題先進県だと思うんですけれども、それに対して何かしらその予算とか政策にどのように反映させていきたいか具体的に教えていただけますか。
(市長)
これもちょっと待っていただけますかね。
まだ今ちょっと発表する段階ではないかなと思います。後で訂正するのもあれなんで。ちゃんと決まってから発表させていただければと思います。
(共同通信社)
共同通信です。
冒頭の挨拶のところで、今年は万博もあったり、去年香港と韓国の直行便も発着するようになったので、徳島をPRしていくというふうにあったんですけれども、何か具体的にどう関わっていくかとか、そういったことはありますか。
(市長)
万博では徳島のブースとかですね、阿波おどりも披露することになっています。当然県もやりますし、その阿波おどりの魅力もしっかり伝えられるのではないかと思います。イーストとくしま観光推進機構もかなり力を入れて関わっていただいておりますので、市と連携して、結果は出るのではないかと思っております。
(読売新聞社)
読売新聞です。
防災について伺いたいんですけれども、今月の17日に阪神淡路大震災から30年になるということで、30年ということでの思いと、地震ということで徳島市も他人事ではないと思いますけれども、改めて今後防災において力を入れていきたいことを教えてください。
(市長)
防災ですね、その地震対応というのは大きな問題だと思ってます。
来週になるんですね。30年ということですけど、あわぎん広場に30年を迎えてということで、市長も来てねというお誘いがありましたんで、そこに行くことにはなっておりますけども、私もこの阪神淡路大震災っていうのは、かなり思い入れが強くて、当時、四国放送で「おはようとくしま」という番組をやっておりました。その当日の朝の本当に地震の認識のなさといいましょうか。
四国放送の社員頑張ったんですよ、朝早起きしてね、ブロックが倒れてるとことかみんな撮影してきて全部放送していったんです。でも、すごい小さな問題だったんです。水道管で水が噴き出てるところがありました。ブロック塀が倒れてるところとか、そういうところを朝スタッフが一生懸命撮影してきて、7時から放送しました。6時前に地震が起きたときに、震度4だったと思いますが、かなり揺れたんですけど、その震度4の被害の情報を一生懸命放送していたんです。というのもですね、神戸あたりがあんなひどい状況になってるっていうのを私達は全く理解してなかった。というのが、私は朝、神戸の方からっていうんで、NHKのラジオ聞いたんですよ。そしたら、平穏ですって言っていたんです。神戸は平穏ですと。真っ暗だったんで、NHKの中にいらっしゃる方からは、ほんまにわからなかったと思うんですね。かなりすごい状況だったけど、今は平穏ですっていう放送を聞いて、そんな大したこともないのかという状況で、徳島県内はこんなことが起こったんだって、皆さん地震に気をつけましょうねみたいな放送をずっと1時間やって、終わって、テレビ見てびっくりですよ。全国放送を見て。もう高速道路は倒れてる、ビルがいっぱい倒れている、火事は起こっている、そんな中で、私達は塀が倒れたみたいな話しかできてなくて、問題意識を持たずにですね、そんなすごいことがすぐ隣で起こっているっていう意識を持たずに、淡路島で起こっているっていう意識を持たずにですね、誰か言ってくれよというふうに思ったんですけど、知らずに放送したというのがものすごく印象に残ってて、その後、私神戸の取材に行きました。もう何も交通機関がなくて、ただひたすら歩いて、徳島出身の人いませんかって、避難所で看板を掲げてですね、人に話を聞いて、もういろんな現場も見てきました。その悲惨さっていうのも、まだ30年経ってますけど、目に焼き付いてます。徳島でも大きい地震は必ず起こるんですよね。それに対して、皆さんにその危機感を持っていただきたいということですね。徳島市としては、具体的な対策プラスですね、いかに危機感を持っていただくかということが大事なんだというのを本当に感じているところです。その地震対策、防災対策っていうのは本当に大事なことだと思っています。
(幹事社・朝日放送)
他よろしいでしょうか。では会見を終わりたいと思います。ありがとうございました。
(市長)
ありがとうございました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。