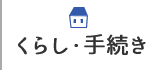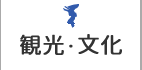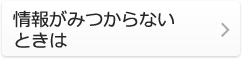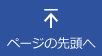月光の夏 ― 戦火に消えた一人の乙女の物語 ―:西條 史朗
最終更新日:2016年4月1日
徳島市佐古一番町 西條 史朗
昭和二十年七月四日早朝、父が召集され不在だから長男として家を守らねばと必死に消火したが、どうしようもなくなり飛び込んだ佐古川からはい上がって見た世界は、一面の焼け野原で所どころから煙が立ち昇り、焼死体が数体転がっている死の世界だった。やがて昇ってきた太陽はすごく大きくて、灼熱した溶鉱炉のような色で十五年の人生で見てきた太陽とは明らかに違っていた。
その化け物じみた太陽の下で弟妹をつれて山に逃げたはずの姉の連絡を待っていると、姉が重傷を負い鈴江病院に入院したとの連絡があり、母と急行(といっても歩いてだが)すると姉は大腿部に爆弾が貫通するという重傷だった。父は軍医として救護に忙しく、顔を見せたのは夕方だったが姉を診て顔色を変えた。直ちに手術が必要なのに病院には手術用の麻酔剤がなく、傷が深くて土にまみれているのに破傷風血清が無かったのである。「とにかく、血清を探してくる。」といって父は出ていったが、深夜に帰ってきた彼の表情は血清探しが失敗であったことを物語っていた。師団司令部の中でも血清は貴重品で、軍医部長の許可がなければ一本も使えず、それも軍人のみで家族使用など論外であり、入隊一ヶ月の新米軍医には薬品を横流しする入手ルートもなく、数本の生理食塩水を手に入れただけで最愛の娘を殺すに等しいことになってしまったのである。
やがて姉は死んだ。その日、昏睡状態となっていた姉が唇を動かしているのに気付いた母が耳を近づけると、「うちな、おとうちゃん、おかあちゃんの子に生まれてよかった。」という無意識からの遺言だった。泣きながら昏睡状態の姉に頬ずりをしていた母は姉の手や指の動きに気付き、それがベートーベンの「月光」の譜であることに気付いた。青春の十六才は、大阪女子医専合格の喜びも名曲を楽しんだ思い出と共にむなしく消え去った。姉は辛うじて焼け残った花柄の浴衣を着て、焼け跡で拾った櫛で髪を
今、姉は空襲下に自分が重傷を負いつつ必死に守った弟、そして父と共に眠っている。葬られたときに姉が身にまとっていたものはただ一枚の浴衣だった。今、彼女は女子医専合格祝いに買ってもらったが戦火で焼けて一度も着る機会のなかった訪問着を着ているだろうか。失われた彼女の世界を眺めているのだろうか。母と私は今でも姉が雲の彼方で「月光」を弾いていると頑固に信じているのだが。
このページに対する連絡先
総務課 文書担当
電話:088-621-5017
FAX:088-654-2116
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。