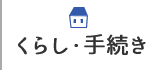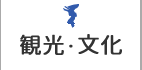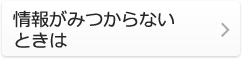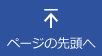徳島大空襲の体験:橋本 富男
最終更新日:2016年4月1日
徳島市南仲之町 橋本 富男
一九四五年十一月、日ごとに寒さが増していく中、徳島大空襲で焼け出され家をなくした人たちは、焼け残った神社のお堂に身を寄せていた。徳島市内に住んでいた私たち家族ももちろん家を焼かれ、そのお堂での生活を余儀なくされていた。お堂では老若男女が雑魚寝して雨露をしのいでいたが、広いお堂は寒く、せめてもの寒さしのぎに粗
日がたつにつれ、終戦時に軍隊から持ち帰った食料も底をつき、食べることもままならない日が続いた。お金があっても何の役にも立たず、家族のためにと意気盛んだった私は、ついには食べるものを探しに闇夜の晩に芋畑へと出かけた・・・。畑の持ち主には申し訳ないと思いつつ背に腹はかえられなかった。
食べるものもなく、人々は、栄養失調で顔が三倍にもはれあがり、ひとり、またひとりと亡くなっていった。ある朝、ひとりの少女が「にいちゃん、うちの母ちゃんが死んだ。」と泣きながらやってきた。私はその亡骸を
身も心も冷えきっていたある日、ひょっと見た娘さんの首筋が
戦前に父親と仕事で出入りしていた県庁も、建物そのものは残っていたものの、中はほとんど焼けていた。そこで頭に浮かんだのは焼け残った配電盤の扉を利用することだった。風呂の底に使うには、その大きさといい、三センチおきに開いた穴が、板を打ち付けるのにぴったりの代物だった。しかし、廃材を使い箱型の風呂を作ったものの、せっかく、くんできた水をはっても、ちょっとしたすき間から水が漏れてしまうのだ。どうしたものかと頭をかかえていると、父親が溝にたまったヘドロのような土を取ってきて、風呂おけに流し込みかき混ぜると、その土がすき間に入り込んで栓の働きをし、水漏れが止まったのである。
風呂の水は神社の井戸からくみ上げ、薪は焼け残った家の柱を使ったため、不自由はしなかった。若い娘さんたちのために風呂の周りに目隠しを作り、すべて完成したときは、みんなでバンザイして喜んだ。一銭のもうけにもならないことだったが、あのときのみんなの笑顔と感謝の気持ちは何物にも代えがたいものがあった。
何もかも消失してしまったあのとき、「何が何でも生き抜かなあかん!」という気持ちだけが生きる支えだった。
以上が私の徳島大空襲の体験である。
このページに対する連絡先
総務課 文書担当
電話:088-621-5017
FAX:088-654-2116
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。